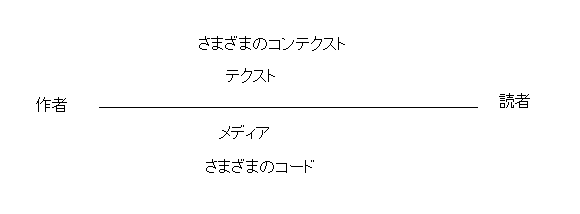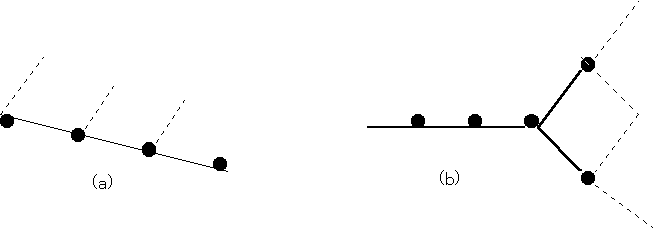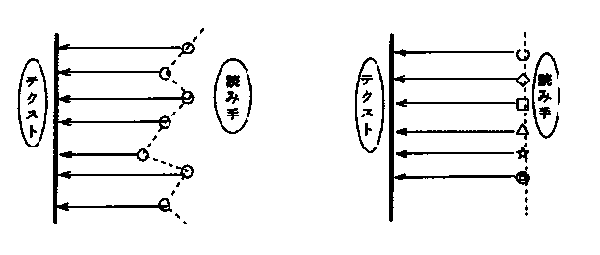ウナギ文のような文は、コンテクストなしでその意味内容を相手に伝えることは難しい。何の文脈もなしに「僕はウナギだ」というと、「Iam an eel.」と解釈されがちである。しかし「何を食べる?」に続く「僕はウナギだ」であれば、「 I will have an eel.」という意味内容が、相手に容易に伝わる。このように、文脈は文を理解する上で重要なものである。そして文は文脈というつながりによって文章というまとまりになりうると考える。言い換えると文章は文脈によってひとつのまとまりとして成り立つと考える。
しかしこの文脈とはいったい何なのか。
たとえば、次の2文における文脈、文どうしのつながり、はどう考えられるのか。
①文と②文は卒論に関することが述べられており、何らかの関係があると思われる。が、この2文並んでいるだけでは文と文のつながりがはっきりしない。ただ同じテーマについて述べられている文を、二つ並べただけで、文章というには何か違和感が起こる。
しかし次の2文ではどうか。
| 備考 | 空所 | 空所 | 空所 | 空所 | 空所 | 空所 | 人物の重要性 | 視点人物は? | どうした | なにを | どのように | 人物設定/その心理状態 | だれが | なぜ | | どこで | いつ |
|---|
| | 1.汽車を降りたのは二人だけだった。 |
| 名詞文 | | | | | | 「ふたり」とは誰なのか? | | 視点人物はだれか? | 降りた | 汽車を | | | ふたりだけ→ふたりとは誰?誰の視点か | | | 汽車→田舎?(の駅)ふたりだけ | 汽車→昔か?
|
| | 2.シャツの襟が汗で汚れるのを防ぐためだろう、顎から手拭いを垂らした年配の駅員が柱に凭れて改札口の番をしていた。 |
| | | | | | | | 駅員は主人公なのか? | | 垂らした/改札口の番をしていた | 手拭いを | 頚から/柱に凭れて | | 年配の駅員/どんな駅員か?(重要か) | シャツの襟が汗で汚れるのを防ぐため | | 手拭いを垂らし、柱に凭れていても構わないような小さな駅 | 汗→夏・具体的にいつ?
|
|---|
| | 3.その駅員の手を押しつけるようにして切符を二枚渡し、待合室をほんの四、五歩で横切ってぼくは外にでた。
|
| | | | | | | ぼくとその連れ | ぼくが主人公か? | ぼくが視点人物 | 渡し/横切って外へ出た | 切符を二枚 | その駅員の手に押しつけるようにして/ほんの四、五歩で | ぼくは駅に関心を持っていない | ぼく→視点人物:ふたりとはぼくとその連れ | なんの目的で来たのか? | | 小さな駅 田舎 | |
| | 4.すぐ目の前を、荷車を曳いた老馬が尻尾で蠅を追いながら通り過ぎ、馬糞のまじった土埃りと汗で湿った革馬具のえた匂いを置いていった。 |
| | | | | 匂いについての丁寧な描写/匂いの持つ意味とはなにか? | | | | | 通り過ぎ/置いていった | 馬糞の交じった土埃と汗で湿った革馬具の饐えた匂いを | 尻尾で蝿を追いながら | | 荷馬車を引いた老馬が | | 荷車・老馬・蝿・馬糞・土埃・汗・革馬具の匂い→田舎・農業の匂い | すぐ(ぼくの)目の前を | |
|---|
| | 5.土埃りと革馬具のえた匂いを深々と吸い込んでいると、弟が追いついてきて横に並んだ。
|
| | | | | 臭くても「深々と」吸い込む「匂いは」ぼくにとって重要なもの | この兄弟は何の目的で来たのか? | ぼくと弟 | | | 吸い込んでいると/追いついて来てぼくに並んだ | 土埃と革馬具の据えた匂いを | 深々と→「匂い」はぼくにとって親しいもの | | (ぼくが)/弟が | | | |
|
| 備考 | 空所 | 空所 | 空所 | 空所 | 空所 | 空所 | 人物の重要性 | 視点人物は? | どうした | なにを | どのように | 人物設定/その心理状態 | だれが | なぜ | | どこで | いつ |
|---|
| | 6.弟は口を尖らせていた。
|
| | | | | | | | | | 尖らせていた | 口を | | 弟の年齢は幼いのか? | 弟は | (なぜ?)
↓ | | |
|
| | 7.ぼくがひとりでさっさと改札口を通りぬけたことが、自分が置いてきぼりにされたことが不満なのだろう。
|
| | | | | | | | | | | | | 置いてきぼりにされる弟→(捨てられる) | | ぼくがひとりでさっさと改札口を通りぬけたことが、自分が置いてきぼりにされたことが不満なのだろう。 | | |
|
| | 8.「思い切り息をしてごらんよ」
|
| 会話文 | | | | | | | | | してごらんよ | 息を | 思い切り | 兄は弟に対して悪気はない | | | | |
|
| | 9.弟はぼくに言った。
|
↑
↓ | | | | 何故弟に息を吸わせるのか?→「匂いの」重要性大 | | | | | 言った | 弟に | | | ぼくは | | | |
|
|---|
| | 10.「空気が馬くさいだろう。
|
| 会話文 | | | 何故説明するのか→弟は「匂い」を知らないから→何故知らないのか | | | | | | 馬くさいだろう | | | | 空気が | | | |
|
| | 11.これがぼくらの生まれたところの匂いなんだ。
|
| 会話文 | | | 生まれたところを教える→弟は生まれたところを憶えていない→生まれてすぐにこの場を出たのか? | →→→→ | 生まれた田舎に久しぶりに戻ってきた→何処から? | | | | ぼくらの生まれたところの匂いなんだ | | | | これが | | | |
|
|---|
| | 12.弟はボストンバッグを地面におろし、顔をあげて深く息を吸い込んだ。
|
| | | | | | | | | | 地面におろし/吸い込んだ | ボストンバッグを/息を | 顔をあげて深く | ボストンバッグを持つ弟→ハイカラ(対田舎):兄を受け入れる弟 | 弟は | | | |
|
| 備考 | 空所 | 空所 | 空所 | 空所 | 空所 | 空所 | 人物の重要性 | 視点人物は? | どうした | なにを | どのように | 人物設定/その心理状態 | だれが | なぜ | | どこで | いつ |
|---|
| | 13.どうだ、この匂いを憶えているだろう?
|
| 兄のセリフ | | | 「匂い」を共有しようとする兄の強い意志 | | | | | 憶えているだろう | この匂いを | | | | | | | |
|
| | 14.「ぜんぜん」
|
| 弟のセリフ | | | | 兄と弟の相反する反応 | | | | | 憶えていない | | ぜんぜん | | | | | |
|
| | 15.孤児院のカナダ人修道士がよくやるように弟は方を竦めて見せた
|
| 特異な情報 | | 「孤児院のカナダ人修道士」はどうゆう関係があるのか?→弟の周りの人:メディア・近所・孤児院にいるのか? | | | | | | | 竦めて見せた | 肩を | 孤児院のカナダ人修道士がよくやるように | | 弟は | | | |
|
| | 16.「別にどうってことのない田舎の匂いじゃないか」
|
| 弟のセリフ | | | | 兄にとって親愛的な匂いを否定する弟「ただの匂い」故郷に対する思いはない | | | | | 田舎の匂いじゃないか | | べつにどうってことのない | 故郷とはかけ離れた弟 | | | | |
|
| | 17.この町を出たときは弟はまだ小さかった。
|
| | 幼くして故郷に出る事の意味は? | 幼くして親を亡くし、孤児院に行ったのか? | ←←←← | ←←←← | 小さいときに故郷に出る。何故出たのか?何処に行ったのか? | | | | まだ小さかった | | | | 弟が | | | | この町を出たときは
|
|---|
| | 18.この匂いが記憶にないのは当然かもしれない。
|
| 兄の心理 | | | | 当然かも知れないが、兄には忘れられない匂い | | | | | 記憶にないのは当然かもしれない | この匂いが | | 弟を理解しようとする兄 | (弟が) | | | |
|
| | 19.でもぼくにはこの馬の匂いと生まれ故郷の町とを切り離して考えることが出来なかった。
|
| | 幼くして故郷を出ることの意味は? | 幼くして親を亡くし、孤児院に言ったのか? | | | 小さいときに故郷にでる→何故出たのか?何処に行ったのか? | | | | まだ小さかったこの馬の匂いと生まれ故郷の町とを| | | ぼくには | | | |
| |
| 読みの作業 | その意図
|
|---|
| 「あくる朝の蝉」 井上ひさし
→タイトルからストーリーを予想し、読みの方向性をある程度決める。 | 全くストーリーを予想しないで読み進めるよりも、多くの情報をつかむことができる(読みの方向性が決まっているということは、何度も読むと、深く作品を読めるのと同じで、叙述から多くの情報をつかむことができる。)しかし、方向性が大きくずれてしまうと、間違った情報を得ることになる。 |
| (1)汽車を降りたのはふたりだけだった。→「ふたりだけ」の「だけ」を強調する理由に注目。書き手の狙いは何なのかを探る。 |
| (2)シャツの襟が汗で汚れるのを防ぐためだろう、頸から手拭いを垂らした年配の駅員が柱に凭れて 改札口の番をしていた。
| |
(3)その駅員の手に押しつけるようにして切符を二枚渡し、待合室をほんの四、五歩で横切ってぼくは外へ出た。
→「ぼくは夏の昼ごろ、いなか」(2・3文より)に「汽車」(1文)に乗ってきたという大まかな様子を掴んでいる。
→また、「ほんの四、五歩で横切っ」た(3文)ことから、ここが小さい駅であることを捉える。
→また、「切符を二枚渡し」(3文)たことから、「ふたり」(1文)は、「ぼく」とその同伴者であるとフィードバックして、情報を補う。さらに、大人であれば自分の分の切符は自分で渡すだろうから、同伴者は「ぼくの子」か「年下の兄弟」と推測している。 | 数字に対して敏感に反応する。数字を境界の信号としている |
| (4)すぐ目の前を、荷車を曳いた老馬が尻尾で蠅を追いながら通り過ぎ、馬糞のまじった土埃りと汗で湿った革馬具の饐えた匂いを置いていった。 | |
(5)土埃りと革馬具の饐えた匂いを深々と吸い込んでいると、弟が追いついてきて横に並んだ
→3文での「ふたり」に対する推測が正しかったことを、確認している。
→「匂い」は場面をイメージするのに役立っている、と「匂い」がこの作品に於いて果たす役割について捉えている。
| ここにおいて、平和な風景と捉える。
田舎を平和なものとする。
自分の読みを、フィードバックして叙述に反映させているところから、自己の読みを修正する準備があることがわかる。
「匂い」がどんな匂いか、ということよりも、舞台設定の一つの道具であると捉えていることから、書き手の意図を意識した読みが行われている。 |
(6)弟は口を尖らせていた。
→口を尖らせている理由が、容易に<明らかに欠如している情報>として、疑問に思う。
→3・4・5文より、「ぼくはさっさと弟を放って歩いていたから」と「弟が口を尖らせていた理由」を推測している。
| 容易にブランクを感じ、それを埋めるような読みを、今後行っていく。
「境界」が十分に捉えられていると思われる。というのは、「ぼく」の視点からは、弟の口を尖らせる理由は理解可能なものであるため、当然ブランクを意識する。状況が十分に、自分の読みの中で、再現されているため、場面の脈絡から欠如した箇所を容易に埋めている。 |
| (7)ぼくがひとりでさっさと改札口を通り抜けたことが、自分が置いてきぼりにされたことが不満なのだろう。 | 7文は、自分の読みを確かめるだけの文になっている。新たな情報を与える文にはならない。 |
| (8)「思いきり息をしてごらんよ」 | |
(9)弟にぼくは言った。
→弟が気づいてない匂いをかがせてやろうとしてている、という「ぼく」の発言の意図を推測する。 | 「ぼく」の視点から場面を再現しいるので、「ぼく」の心理も理解可能な領域となる。従って、そこにブランクのスペースを作り、心理を推測する。 |
| (10)「空気が馬くさいだろう。 | |
(11)これがぼくらの生れたところの匂いなんだ」
→場面の舞台であるこの田舎が、生まれ故郷であるという認識をもつ。故郷が都会と対極にある田舎である?
→「ぼく」に対して、性格的に人物設定する。感情豊か、弟を放ってまで故郷を感じようとする、のんびりや。 | 生まれ故郷が「匂い」をもつ田舎であると認識する。
これまで述べられてきた情報の範囲内で、人物設定している。年齢や、社会的立場といった面での推測は避けている。テクストの内に読み手の視点はあり、外に出ることはない。 |
(12)弟はボストンバッグを地面におろし、顔をあげて深く息を吸い込んだ。
→「ボストンバッグ」から長期滞在を推測し、夏休みの里帰りの場面とする。
|
これまでの「いなか」「饐えた匂い」などのイメージとは異質な「ボストンバッグ」に注目。そこに書き手が意図的に含めた情報があるだろうと推測する。 |
| (13)「どうだ、この匂いを憶えているだろう?」 | |
(14)「ぜんぜん」
→ぼく=田舎育ち
弟=生まれてすぐに田舎を離れる(都会育ち)
故郷を懐かしまない | 「ぼく」と「弟」が反対の感情であることを捉える |
(15)孤児院のカナダ人修道士がよくやるように弟は肩を竦めてみせた。
→喩えにしては具体的すぎる「孤児院のカナダ人修道士」に、違和感を感じる。
| 限定した人物を、何の予告もなしに登場させるため、読み手は信頼感を揺り動かされる。しかし、その登場が、喩えに用いられるため、どこまでこの情報を切り捨てずに、留めておけるかが、読みの方向を分けることになるだろう。違和感を感じるが、どう処理するかは、明らかでない。 |
(16)「べつにどうってことのない田舎の匂いじゃないか」
→弟は兄とは反対の都会っ子であると認識している。 | |
(17)弟がこの町を出たときはまだ小さかった。
→幼いうちにこの地を出るということは、自分の意志では無理で、「弟」は親の都合により、この地を出たと推測する。 | |
以下未完了
(18)この匂いが記憶にないのは当然かもしれない。
(19)でもぼくにはこの馬の匂いと生れ故郷の町とを切り離して考えることは出来なかった。
| |
| 読みの作業 | 作業の意図 |
|---|
| 「あくる朝の蝉」 井上ひさし | |
(1)汽車を降りたのはふたりだけだった。
→「ふたり」に注目する。二人、あるいはその内の一人を中心に、ストーリーが展開していくのではないかと想定。
→駅の風景、ふたりに関する叙述を想定。 | 「ふたり」に注目するが、その推測を決定的なものにはしないで、修正の余地を保持したまま読み進める。
可変項を(1)文の場景が見える地点におけば、「ふたり」は風景の一部として処理できるが、二人の内の一人に視点を置く可能性も残しているため、場所か人物かという二択を設定する。 |
(2)シャツの襟が汗で汚れるのを防ぐためだろう、頸から手拭いを垂らした年配の駅員が柱に凭れて 改札口の番をしていた。
→終戦直後の山奥、小さな駅
| |
(3)その駅員の手に押しつけるようにして切符を二枚渡し、待合室をほんの四、五歩で横切ってぼくは 外へ出た。
→「ぼく」は視点人物であり、語り手の役割をも担うとする。
→「ぼく」は子どもであっても、そう幼くはないと推測する。 | 「ぼく」が語り手の役割を担うとすることで、「ぼく」の視界は多くのものを取り込むことができると想定している。従って(1)文において自らを「ふたり」という全知的視点で語ることも可能であると解釈する。
また、「ぼく」の年齢を推測することとは、作品世界に読み手が身を寄せているため、人物設定が行われている。 |
(4)すぐ目の前を、荷車を曳いた老馬が尻尾で蠅を追いながら通り過ぎ、馬糞のまじった土埃りと汗で湿った革馬具の饐えた匂いを置いていった。
→細かな描写文であるため、そこにブランクを感じとる。老馬を曳く人間は?荷台には何が?
→「荷車」「老馬」から時代設定に関して現代ではないとする。
→山間の小さな駅の前で立っている男という、映像的な場面を想定している。
| 読み手は作品世界に身を寄せ、場面を映像的に再現しようとしているため、再現できない部分はブランクとして感じ取られる。
想像している場面は、登場人物を組み込んだ形で、映像的に再現している。
|
(5)土埃りと革馬具の饐えた匂いを深々と吸い込んでいると、弟が追いついてきて横に並んだ。
→弟の登場により、(3)文の読みにフィードバックして、二枚渡した切符の一枚は弟の分であったことを再確認する。
→ぼくと弟の人物設定に関する情報を求める。年齢差は?親、または親族は?ふたりの行き先は?
→「ぼく」が弟の分まで切符を渡してやるような年齢差、つまり切符を代わりに渡してやらないと行けないような弟がいる「ぼく」は、歳の差があったとしても、大人ではないと推測する。
→「匂い」はふたりにとって嗅ぎ馴れていて、気嫌う匂いではないか、やはり臭い匂いなのか、「匂い」と二人の関係についてブランクを感じる。
| (3)文で「切符を二枚渡し」という情報を切り捨てていなかったことが分かる。自分の読みをフィードバックして再確認することで、枠の形成が関係的に行われている。
弟の登場によって、ぼくと弟は登場人物の中で重要な位置にあるとし、ふたりの人物設定に重要性を感じる。その結果、ふたりの年齢を推測し、そこから親の存在、家族構成に至るまで、情報を求めようとする。この読みが結果的に、ふたりが孤児院にいるという読みにつながるのであろう。
細かな「匂い」の描写から、ふたりにとっての「匂い」の重要性を考える。 |
(6)弟は口を尖らせていた。
→弟の口を尖らせる理由にブランクを感じる。
→弟の感情を露骨に仕草に出すことから、弟の年齢が、幼いと解釈する。 | 構文的なブランクであるが、そこから、「ぼく」も同じことに対して不満なのか、その理由ではなく、「ぼく」との関係に注目する。 |
(7)ぼくがひとりでさっさと改札口を通り抜けたことが、自分が置いてきぼりにされたことが不満なのだろう。
→弟を置いてきぼりにした理由、駅を出て待っていたのに何故不満なのか、といった「ふたり」の関係に注目する。 | 兄と弟それぞれの対応に注目している。ここでは、弟が不満に思う理由と読み手の常識との間にギャップが生じ、そのギャップを解消するような意味づけを求める。 |
| (8)「思いきり息をしてごらんよ」 | |
(9)弟にぼくは言った。
→「ぼくに弟は言った。」との違いを感じ、書き手の意図することを探ろうとする。 | |
| (10)「空気が馬くさいだろう。 | |
(11)これがぼくらの生れたところの匂いなんだ」
→「ぼく」が弟に匂いを教えているということは、弟は生まれたところの匂いを知らないからで、その理由は何かブランクを感じる。
→降りた駅は、ふたりの故郷の駅であった、とフィードバックして、関係づける。 | |
(12)弟はボストンバッグを地面におろし、顔をあげ て深く息を吸い込んだ。
→ボストンバッグの中身は何か?また、ぼくは荷物を持っているのか?といった疑問を抱く。 | ボストンバッグからギャップが生じ(田舎のイメージからは離れたイメージを持つ言葉であるため)、そこに重要性を持つ。その結果、鞄の中身に注目する。また、「ぼく」と弟を常に対照的に関係づけてきたことから、「ぼく」は「ボストンバッグ」に対する荷物を持っているのかという疑問につながる。 |
| (13)「どうだ、この匂いを憶えているだろう?」 | |
(14)「ぜんぜん」
→兄は物覚えがつく頃、まだこの町に暮らしていたが、弟の方は物覚えがつく前にこの町を出たと推測する。そこから、二人のふたりの年齢差を強く求める。また、ふたりがこの町を去ってからどのくらいの時間が流れているのか、つまり「今」がいつなのか、舞台設定時間に注目する。
→降りた駅は、ふたりの故郷の駅であった、とフィードバックして、関係づける。
| ここでも、ふたりは対照的に関係づけられている。兄は、この町のことを覚えているのに対して、弟は憶えていないと対照的に位置付ける。 |
(15)孤児院のカナダ人修道士がよくやるように弟は肩を竦めてみせた。
→「孤児院のカナダ人修道士」と「ふたり」の関係にブランクを感じる。 | カナダ人修道士は、喩えに使われたものであるが、その存在を登場人物として捉え、二人との関係に疑問を持つ。 |
(16)「べつにどうってことのない田舎の匂いじゃないか」
→兄と弟の対立的な関係を想定する。
| |
以下未完了
(17)弟がこの町を出たときはまだ小さかった。
(18)この匂いが記憶にないのは当然かもしれない。
(19)でもぼくにはこの馬の匂いと生れ故郷の町とを切り離して考えることは出来なかった。 | |
| 読みの作業 | 作業の意図 |
|---|
「あくる朝の蝉」 井上ひさし
→井上ひさしの作品から、おもしろい話と想定する。 | おもしろいとは滑稽の意。
|
(1)汽車を降りたのはふたりだけだった。
→駅に対する意味づけの必要性を感じる。 | 「だけ」が、駅の様子(乗客がふたりだけという閑散とした駅)を意味づけるものになると意識する。しかし、その様子を想定することはない。そして、「ふたり」はある情景の中の細部として、切り捨てる情報となる。 |
(2)シャツの襟が汗で汚れるのを防ぐためだろう、頸から手拭いを垂らした年配の駅員が柱に凭れて改札口の番をしていた。
→30年前ぐらいの平和な頃、田舎の木造駅舎を場面舞台として想定。
| 駅員が「番をしていた」などから、平和なイメージが想定され、そこから戦後という時代を設定。同時に田舎というイメージが木造の駅舎を想定。 |
(3)その駅員の手に押しつけるようにして切符を二枚渡し、待合室をほんの四、五歩で横切ってぼくは外へ出た。
→(1)の「ふたり」に、注目し直す。 | (1)で切り捨てた「ふたり」へ注目し直す。 |
(4)すぐ目の前を、荷車を曳いた老馬が尻尾で蠅を追いながら通り過ぎ、馬糞のまじった土埃りと汗で湿った革馬具の饐えた匂いを置いていった。
→何度も繰り返し読んで、文意を読みとる。何度も読むことで、描写されている情景を忠実に再現しようとする。
| 文の構成が複雑であり、かつ丁寧な描写のため、読みのリズムを狂わすことになる。その結果、読み飛ばされてしまう場合もあるが、ここでは、丁寧な読みを行うことになる。 |
(5)土埃りと革馬具の饐えた匂いを深々と吸い込んでいると、弟が追いついてきて横に並んだ。
→「ふたり」が「ぼく」と「弟」であるとわかる。「ふたり」が全くの他人であると考えていたために、修正をする。
→土臭い匂いを想像する。「匂い」に対して、意味づけを行うことはない。
| (1)において、場所に注目していたため、「ふたり」に関する想定が行われていない。ここではじめて、「ふたり」を意識し、読みの方向性が修正される。また、(3)の「切符を二枚」についても読みとられていない。これは、「ぼく」の登場という、最も重要な情報が提示されたために、細部の情報提示の言葉が、見過ごされているためである。
叙述の外側にある書き手の意図から意味解釈することはなく、叙述内のつまりテクスト内においてのみ、解釈がなされている。 |
(6)弟は口を尖らせていた。
→弟は怒って口を尖らせており、この地へやってきたことを不満に思っていると解釈する。また、口を尖らせるという幼い行動から、弟の年齢を想定する。 | 口を尖らせた理由は、文の構造上からも、ブランクとして意識されるものであり、その理由を推測する。しかし、これまでの文脈から、駅を降りた弟が怒っているとなれば、この地に降りたことが不満であると解釈する。明示された情報から作り上げられた文脈に則って、解釈がなされている。 |
(7)ぼくがひとりでさっさと改札口を通り抜けたことが、自分が置いてきぼりにされたことが不満なのだろう。
→(3)を読み返し、読みを修正する。 | 「改札口」が、(3)文での読みを修正させることになる。 |
| (8)「思いきり息をしてごらんよ」 | |
(9)弟にぼくは言った。
→「弟がぼくに言った。」と誤読している。
→「ぼく(弟)」の発言に疑問をもつ。そして、読みは、いやな「匂い」を強調する方向へ進む。 | (5)の「深々と吸い込んでいる」を読みとっていないため、「ぼく」の発言は「匂いが臭い」と強調することになっている。 |
| (10)「空気が馬くさいだろう。 | |
(11)これがぼくらの生れたところの匂いなんだ」
→この場所がふたりの生まれたところであると認識する。そして、現在ふたりが生まれ地に住んでいないと推測する。 | |
(12)弟はボストンバッグを地面におろし、顔をあげて深く息を吸い込んだ。
→弟の発言によって、弟が息を吸い込んでいることに、矛盾を感じ、(9)の読み違いに気づく。同時に、匂いの臭さも修正され、匂いが生まれた地を確認するものだという認識に変わる。 | 現在進行している枠造りに、何らかの矛盾が起こった場合に、その修正を行う。その矛盾は、ギャップの一つであり、枠造りの方向が向かっている軸上の情報と矛盾する情報が得られたために起こる。読み手の視界に入らない、つまり注目していない情報に対しての矛盾は読み落とされてしまう。 |
| (13)「どうだ、この匂いを憶えているだろう?」 | |
(14)「ぜんぜん」
→兄と弟の生まれ故郷に対する執着の違いを認識する。
→弟はこの地へ来ることに、積極的ではないと解釈する。 | 「ぜんぜん」の素っ気ない言葉が、この地に来る事に対する素っ気なさと解釈する。 |
(15)孤児院のカナダ人修道士がよくやるように弟は肩を竦めてみせた。
→「孤児院のカナダ人修道士」がどう関係しているのか、また、その仕草の具体的な様子が分からない、さらに、何故肩を竦めるのかという疑問につながる。また、飛躍した喩えの情報を、読みの枠へ当てはめるように、意味づけを行うことはない。
| 喩えが、枠造りの視界から飛躍しすぎていて、その具体的な様子が理解できない。そのため、弟が「ぜんぜん」知らないと肩を竦める状態が、想定できない。 |
(16)「べつにどうってことのない田舎の匂いじゃないか」
→どうでもよい、という関心のなさは、この地に対するもので、それが派生して、匂いに対しても無関心であると解釈する。
→(2)における「田舎」という推測が正しかったとする。
| 匂いに対する無関心さを、これまでの解釈の枠組み上にのせて捉える。
場面舞台の決定が引き続き行われている。(2)文における推測は、確認を要する程度の確信を伴うものであった。つまり、推測は明示的な情報になるまで、確信を下されない、不安定な状態にある。 |
(17)弟がこの町を出たときはまだ小さかった。
→(13)(14)での推測を確認する。(町を出たときに弟は幼なかった)。 | (16)同様、これまでの推測は不安定な状態で持ち越されているため、その確認を行う活動を行うにとどまる。そのため、与えられた情報から、ブランクを設定して、言外の情報を得る活動には至らない。 |
(18)この匂いが記憶にないのは当然かもしれない。
→匂いとぼく、匂いと弟の関係を明示されたとおりに、再確認する。 | 言外の情報を得るという活動は行われない。 |
(19)でもぼくにはこの馬の匂いと生れ故郷の町とを切り離して考えることは出来なかった。
→「ぼく」の生まれ故郷に対する思いが深いと解釈する。 | 「切り離して」という言い回しが、故郷に対する想いの深さを感じ取らせているのだろうか。 |
| 読みの作業 | 作業の意図 |
|---|
| 「あくる朝の蝉」 井上ひさし | |
(1)汽車を降りたのはふたりだけだった。
→「ふたり」が何をするか、どこに行ったかがこの先に書かれていると推測する。
| 「ふたり」に関する情報を期待する。しかし、推測は行わない。 |
(2)シャツの襟が汗で汚れるのを防ぐためだろう、
頸から手拭いを垂らした年配の駅員が柱に凭れて 改札口の番をしていた。
→終戦直後、いなか町 | |
(3)その駅員の手に押しつけるようにして切符を二枚渡し、待合室をほんの四、五歩で横切ってぼくは外へ出た。
→「ふたり」の内の一人が男である。
| 「ぼく」から男であることは明らかである。この明らかな情報は受け入れるが、「ぼく」から年齢を推測したりする事はない。明示された情報のみを受け入れる。 |
(4)すぐ目の前を、荷車を曳いた老馬が尻尾で蠅を
追いながら通り過ぎ、馬糞のまじった土埃りと汗で湿った革馬具の饐えた匂いを置いていった。 | |
| (5)土埃りと革馬具の饐えた匂いを深々と吸い込んでいると、弟が追いついてきて横に並んだ。 | |
(6)弟は口を尖らせていた。
→口を尖らせた理由は何か疑問を持つ。 | 構文的にブランクが発生するため、疑問を持つ。 |
| (7)ぼくがひとりでさっさと改札口を通り抜けたことが、自分が置いてきぼりにされたことが不満なのだろう。 | |
| (8)「思いきり息をしてごらんよ」 | |
| (9)弟にぼくは言った。 | |
| (10)「空気が馬くさいだろう。 | |
(11)これがぼくらの生れたところの匂いなんだ」
→どこからか、生まれ故郷に帰ってきたことを認識する。 | どこからか生まれ故郷に戻ってきたとして、一体何処から戻ってきたのかその場所は限定されない。単に「どこからか」というその場所が存在することだけを想定する。 |
(12)弟はボストンバッグを地面におろし、顔をあげて深く息を吸い込んだ。
→ボストンバッグから、長い滞在を推測する。 | |
| (13)「どうだ、この匂いを憶えているだろう?」 | |
| (14)「ぜんぜん」 | |
(15)孤児院のカナダ人修道士がよくやるように弟は肩を竦めてみせた。
→喩えられる様子が分からない。 | |
(16)「べつにどうってことのない田舎の匂いじゃないか」
→談話描写から兄に反抗的な態度をとると解釈する。
→弟の年齢は、3〜5才ぐらいを想定していたが、
この談話から匂いが田舎の匂いだと判断できる年齢、つまりもう少し大きい子どもだと解釈する。 | このような発言は、関係がうまくいっているふたりの間でなされるものではない、という読み手の経験から、弟の態度が反抗的であると解釈する。
さらに、この発言が3〜5歳児からはなされないと判断する。これも、読み手の経験に関わるもので、読み手によっては、(12)文から、ボストンバッグを運ぶことのできる年齢として、弟の年齢を想定する場合もある。しかし、この読み手には、ボストンバックという情報は、弟の年齢を決定するものではなかった。しかし、ここにきて、弟の年齢に関して想定していた情報にギャップが現れ、推測を修正することになる。
|
(17)弟がこの町を出たときはまだ小さかった。
→弟がこの町を出た理由を推測することはなかった。あえて、想定すれば、弟は田舎臭さがイヤで、出ていったと推測する。その結果、弟はこの町は好きではなかったと想定する。 | 弟が町を出た理由は推測を求めるブランクとして、読み手の中には存在しなかったために、外的刺激から推測を求めた場合、その推測は一時的な埋め合わせになる。 |
| (18)この匂いが記憶にないのは当然かもしれない。 | |
(19)でもぼくにはこの馬の匂いと生れ故郷の町とを切り離して考えることは出来なかった。
→弟と対照的に、兄は自分の生まれた町を誇りに思っているとし、ふたりの対立関係が成立する。そして、兄はこの町の良さを弟にも分からせようとしている、と解釈する。
| (16)文から(19)文までで、ふたりの感情の対立関係が成立する。それに伴い、この作品が、今後ふたりの対立を 解消していく方向に進むと想定してゆく。 |
| 読みの作業 | 作業の意図 |
|---|
「あくる朝の蝉」 井上ひさし
→井上ひさしの作品ということから、何か含みのある、まじめな作品だと推測する。 | 「含みがある」とは、テクストを生成するには、言語情報のみでは意味解釈できない、さまざまな読みの活動を強いられるものだと捉えている。 |
(1)汽車を降りたのはふたりだけだった。
→降りた乗客に対して、乗った乗客の情報を求める。が、語りの視点は、「ふたり」へ向けられていくことは、認識して、この先に「ふたり」に関する情報を期待する。
| 語りが焦点を合わせる境界の外を、常に把握しようとする思考が働いている。作者名に対する推測において、「含みがある」と感じているため、語りの視点に惑わさないで、より広い視界を保とうとする意志が見受けられる。 |
(2)シャツの襟が汗で汚れるのを防ぐためだろう、頸から手拭いを垂らした年配の駅員が柱に凭れて改札口の番をしていた。
→明治か昭和初期、夏、人気のない、汚い駅 戦前、きたない駅とは、テクスト内
の情報から得たものではなく、テクスト外に抱く、個人的なコードによるイメージから来るものであろう。 | |
(3)その駅員の手に押しつけるようにして切符を二枚渡し、待合室をほんの四、五歩で横切ってぼくは外へ出た。
→「切符を二枚」から、「ぼく」が「ふたり」のうちの一人で、もう一人に対して、主導権を握っている立場にあると推測する。 | |
(4)すぐ目の前を、荷車を曳いた老馬が尻尾で蠅を追いながら通り過ぎ、馬糞のまじった土埃りと汗で湿った革馬具の饐えた匂いを置いていった。
→描写の内容に対して、疑問を抱く。
→細かな描写から、強く田舎という印象を受ける。
| 描写される場景を再現する過程において、読み手自身の現在では再現不能な箇所に、疑問を抱いている。つまり、再現不可能なものに対しては、不信感を抱くことになり、受け入れを拒む。 |
(5)土埃りと革馬具の饐えた匂いを深々と吸い込んでいると、弟が追いついてきて横に並んだ。
→(4)より、「匂い」に対して、マイナスイメージを抱いていたため、「深々と吸い込」む行動に、疑問を憶える。また、その理由を、ぼくにとって懐かしい匂いであるため、と推測する。 | |
| (6)弟は口を尖らせていた。 | |
| (7)ぼくがひとりでさっさと改札口を通り抜けたことが、自分が置いてきぼりにされたことが不満なのだろう。 | |
| (8)「思いきり息をしてごらんよ」 | |
| (9)弟にぼくは言った。 | |
| (10)「空気が馬くさいだろう。 | |
(11)これがぼくらの生れたところの匂いなんだ」
→ふたりは田舎に帰省している。弟にとっては、兄が弟に、ここが生まれた場所だと、教えていることから、初めて訪れる場所であると解釈する。
| 「いなか」を、「生まれ故郷」という意味と、都会に対する「田舎」という意味との両方を混在させて解釈している。これは、読み手と書き手の間で異なる意味生産が行われているためだと考えられる。書き手が意味する内容が「いなか」という言葉によって、読み手に伝達されていないことになる。読み手の中では、生まれ故郷とは常に田舎であるという自明の真理として、認識されている。そのため、「ぼく」の発言は、「ぼくらの生まれ故郷は田舎である」ではなく、「この地がぼくらの生まれ故郷である」という解釈になる。 |
| (12)弟はボストンバッグを地面におろし、顔をあげて深く息を吸い込んだ。 | |
| (13)「どうだ、この匂いを憶えているだろう?」 | |
(14)「ぜんぜん」
→ぼくと弟の匂いに対する記憶の違いが、ふたりの年齢差を意識させることになる。
| ふたりの「匂い」に対する心情に注目するのではなく、「匂い」に対する心情の違いから、人物設定へと目を向ける。 |
(15)孤児院のカナダ人修道士がよくやるように弟は肩を竦めてみせた。
→孤児院にいたのだろうかという推測がすぐさま働く。 | |
(16)「べつにどうってことのない田舎の匂いじゃないか」
→弟のことばからは、彼が生意気であるという印象を受けるものになる。 | |
(17)弟がこの町を出たときはまだ小さかった。
→(15)の推測より、孤児院に入るため、この地を去ったと解釈する。
→「孤児院」ということから、親の状況を求める。 孤児院=ふたりは孤児である、とい
う解釈にはつながっていない。あるいは、孤児であったとしても、親の死因に関する情報を求めていると思われる。 | (15)の推測はかなり、妥当性の高いものとして、捉えられている。そのため、すぐさま、弟がこの町を去った理由を、推測する思考へつながる。 |
| (18)この匂いが記憶にないのは当然かもしれない。 | |
| (19)でもぼくにはこの馬の匂いと生れ故郷の町とを切り離して考えることは出来なかった。 | |